公害防止(大気)ばいじん・粉じん特論の「電気集じん装置測定」に関する覚えるポイントをまとめました
特徴
- 構造が簡単で可動部分が少ない
- 爆発性ガスや可燃性ダストは静電気などで発火し、爆発する恐れがあるため適していない
- コロナ電流密度は、一般に0.3mA/m2程度
- 一般的な乾式電気集じん装置内の基本流速は0.5~2m/s程度
- 通常、粒子径0.1~1µmのサブミクロン粒子に対して部分集じん率が低くなる
- 圧力損失は200Pa程度以下
微粒子の帯電
① 電界帯電:イオンが電気力による電気力線に沿って輸送されて粒子に付着し帯電
② 拡散帯電:イオンが熱拡散運動によって輸送されて粒子に付着し帯電
- 粒子径が2µm以上では電界帯電が支配的、2μm以下では拡散荷電が支配的
- 粒子帯電量は、誘電定数・粒子表面積・電界強度に比例する
- 粒子帯電量は、電界荷電では粒子径の2乗に比例、拡散荷電では粒子径の1乗に比例
集じん率の推定式$η$(ドイッチェの式)
$$η=1-exp(-\frac{ω_{e}A}{Q})$$
$η$:集じん率[-]、$ω_{e}$:分離速度[m/s]、$A$:有効集じん面積[m2]、$Q$:処理ガス量[m3/s]
帯電粒子の移動速度
電界中の帯電粒子はクーロン力$F$を受ける
$$F=qE$$
粒子がクーロン力で移動するときに受けるガスの抵抗力はストークスの法則で決まる
$$F_{s}=\frac{3πμd_{p}v_{e}}{C_{m}}$$
クーロン力とガスの粘性抵抗力が釣り合うとき($F=F_{s}$)の粒子の移動速度$v_{e}$
$$v_{e}=\frac{qE}{3πμd_{p}}C_{m}$$
$F$:クーロン力[N]、$q$:粒子の帯電量[C]、$E$:電界強度[V/m]、$μ$:ガス粘度、$d_{p}$:粒子径、$v_{e}$:粒子の移動速度[m/s]、$C_{m}$:カニンガム補正係数
逆電離現象
逆電離現象とは
集じん電極に付着したダスト層の見かけ電気抵抗率が109Ω・m以上と高い場合に、ダスト層を流れる電流が増加すると層内に著しく高い電解を生じる。これがダスト層の絶縁破壊電界強度を超え、ダスト層内で絶縁破壊を引き起こす現象
逆電離現象を解消する方法
- ダスト層をなくす
- 温度を調整して、ダスト層の見かけ電気抵抗率を下げる
- 間欠荷電により、ダスト層を流れるイオン電流密度を下げる
異常再飛散
異常再飛散とは集じん電極上に付着・堆積したダストがガス中に飛散する。
電気抵抗率が102Ω・m以下で起こる。
装置種類の比較
| 円筒形と平板形 | 平板形が広く用いられる |
| 垂直形と水平形 | 中容量以上では水平形が用いられる。 垂直形はガス流量が大きいと均一分散が困難。 |
| 乾式と湿式 | 湿式の方が集じん性能が高い |
| 一段式 | ガスの荷電と集じんを一緒に行う。 再飛散防止に有効で大容量の産業用装置として用いられる。 見かけ電気抵抗率が非常に高い場合に起こる、逆電離現象を避けることは困難。 |
| 二段式 | 荷電部と集じん部を分けて行う。 逆電離を避けられる。 集じん部の電極間隔を狭くすることで、集じん電極面積を大きくすることができ、装置の小型化が可能。 家庭用の空気清浄器などに用いられる。 |
見かけの電気抵抗率$ρ_{d}$
電気集じん装置の集じん率$η$は、ダストの見かけ電気抵抗率$ρ_{d}$に依存する。
$ρ_{d}$への排ガスの影響因子としては温度・水分・三酸化硫黄の付着がある。
運転管理
- 運転開始時には、排ガス導入前に碍子管表面を十分乾燥する
- 高圧回路の絶縁抵抗が100MΩ以上であることを確認する
- 各部が十分乾燥した後、コロナ放電を開始する
- 停止時は、処理ガスの導入を停止後、電極への通電を停止する
- つち打ち装置は、開始時は自動運転にしてから処理ガス導入、停止時は電極への通電停止後、40 分以上は運転する
その他の集じん装置
遠心集じん装置(サイクロン)【公害防止(大気) ばいじん・粉じん特論】 – 【めざせ一発合格】工場資格まとめ
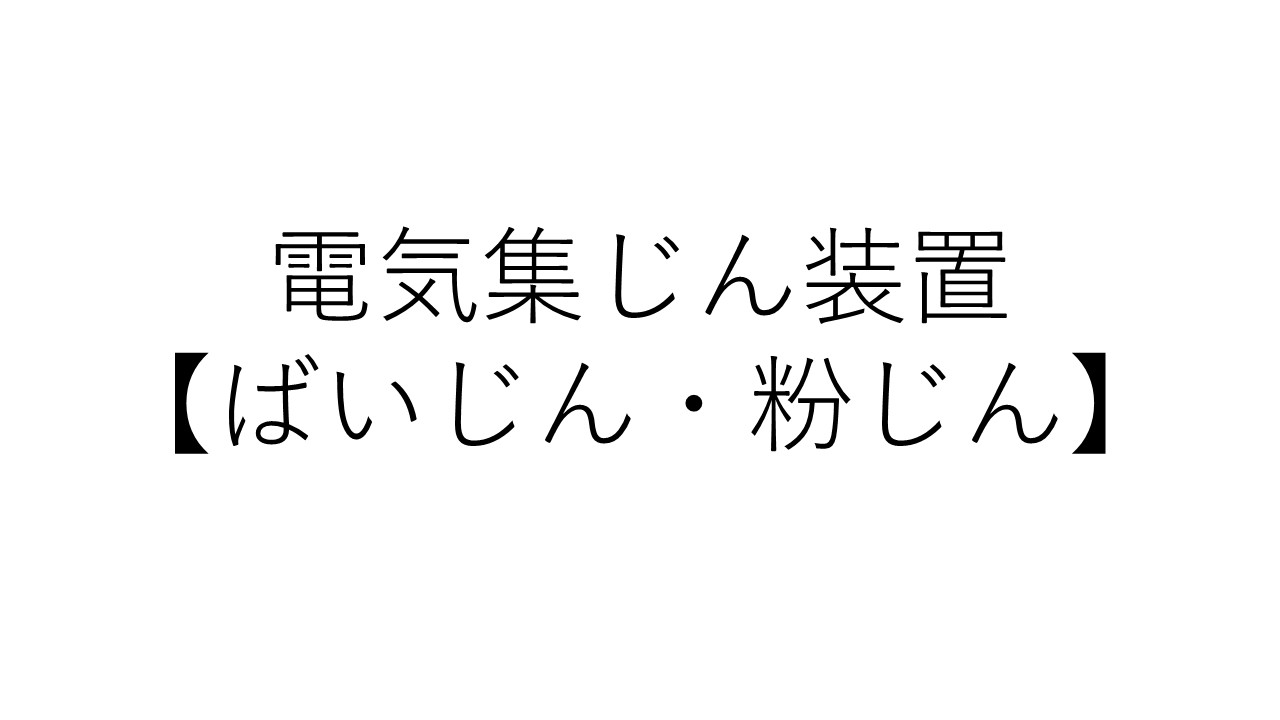
コメント