公害防止(大気)大気有害物質特論の「有害物質の特徴」に関する覚えるポイントをまとめました

分析方法の概要・使用する溶液・妨害物質は似た単語が多いため混乱しますが、正確に覚えましょう
有害物質とは
物の燃焼・合成・分解・そのほかの処理に伴い発生する物質のうち、人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある5物質
有害物質の発生源
| 製品 | 発生する有害物質 | |
|---|---|---|
| クリスタルガラス リサージ | 鉛 | リサージ:クリスタルガラスの原料 リサージとは黄~橙色で主成分は酸化鉛 |
| 亜鉛 | カドミウム | 亜鉛の原料である亜鉛鉱はカドミウムを含む |
| 中性子遮断ガラス | カドミウム | 原料として硫化カドミウムや炭酸カドミウムを用いる |
| 溶成りん りん酸(湿式法)れんが | ふっ化水素 | りんは原料にふっ素を含む りん酸の原料であるリン鉱石は数%のふっ素を含む |
| アルミニウム | ふっ化水素 | アルミニウムの製錬ではアルミナを電気分解して得る その工程で氷晶石(Na3AlF6)やふっ化アルミニウムを用いるためふっ化水素を生じる |
| 活性炭 (塩化亜鉛活性化法) | 塩化水素 | 焼成時に塩化水素発生 |
| 過りん酸石灰 | ヘキサフルオロけい酸 |
有害物質の分析方法
ふっ素化合物の分析方法
ふっ素化合物分析方法について
ふっ素化合物の測定方法は3種類であり、下記の項目は共通で該当する
- 吸収液:水酸化ナトリウム溶液
- 標準液の調整はふっ化ナトリウムを用いる
- 妨害物質Al3+やFe3+による影響が大きい場合は、水蒸気蒸留によりふっ素イオンを分離する
- 定量範囲:イオンクロマトグラフ法<ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法<イオン電極法
①イオンクロマトグラフ法
試料ガス中のふっ素化合物を吸収液に吸収させた後、吸収液の一定量に陽イオン交換樹脂を加え二酸化炭素を除いた空気または窒素を通気して前処理を行う
この液をイオンクロマトグラフに導入し、クロマトグラフを記録する
②ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法
試料中のふっ素化合物を吸収液に吸収させた後、緩衝液を加えてpHを調整
ランタン溶液、アリザリンコンプレキソン溶液およびアセトンを加えて発色させ吸光度を測定
③イオン電極法
試料ガス中のふっ素化合物を吸収液に吸収させた後、イオン強度調製用緩衝液を加えて、ふっ化物イオン電極を用いて測定
- 妨害物質の影響は濃度の極端に異なる2種類のイオン強度調製緩衝液を用いて判定する
- 検量線はふっ化物イオン標準液の濃度(対数)と電位をプロットする
塩素の分析方法
定量範囲:ABTS吸光光度法<PCP吸光光度法<IC法
①ABTS吸光光度法
2, 2’-アジノビス(3-エチルベンゾチアゾリン‐6‐スルホン酸)吸光光度法
試料ガス中の塩素を2, 2’-アジノビス(3-エチルベンゾチアゾリン‐6‐スルホン酸)吸収液に吸収発色させ、吸光度(400nm)を測定し、試料ガス濃度を求める
妨害物質:NO2
②PCP吸光光度法
4-ピリジンカルボン酸‐ピラゾロン吸光光度法
試料ガス中の塩素をp-トルエンスルホンアミド吸収液に吸収して、クロラミンTに変えた液を分析用試料溶液とする
これに少量のシアン化カリウム溶液を加えて塩化シアンとした後、4-ピリジンカルボン酸‐ピラゾロン溶液で発色させ、吸光度(638nm)を測定し、試料ガス濃度を求める
③IC法
イオンクロマトグラフ法
試料ガス中の塩素をp-トルエンスルホンアミド吸収液に吸収して、クロラミンTに変えた液を分析用試料溶液とする
これに少量のシアン化カリウム溶液と水酸化カリウム溶液を加えてシアン酸イオンとした後、イオンクロマトグラフ法で測定し、ガス濃度を求める
- 溶離液:炭酸水素塩‐炭酸塩溶液、水酸化カリウム溶液
- サプレッサー:バックグラウンドとなる溶離液の電気伝導度を低減する装置
- 塩素標準液中の有効塩素はチオ硫酸ナトリウム溶液による滴定で求める
- 硫化物などの還元性ガスの影響を受けるが、NO2の影響は受けない
塩化水素の分析方法
定量範囲:イオンクロマトグラフ法<イオン電極<硝酸銀滴定
①イオンクロマトグラフ法
試料ガス中の塩化水素を水に吸収させた後、イオンクロマトグラフで測定
- 塩化物イオン、硝酸イオン、亜硫酸イオン、硫酸イオンなどを同時に定量できる
- 試料ガス中に硫化物等の還元性ガスが高濃度に共存するとその影響を受ける
- 塩化物イオン標準液の調整には、塩化ナトリウムが用いられる
- 検出器:電気伝導度検出器
②硝酸銀滴定法
試料ガス中の塩化水素を水酸化ナトリウム溶液に吸収させた後、微酸性にして硝酸銀溶液を加え、チオシアン酸アンモニウム溶液で滴定する
試料ガス中に二酸化硫黄、その他のハロゲン化物、シアン化物、硫化物が共存すると影響を受ける
③イオン電極法
試料ガス中の塩化水素を硝酸カリウム溶液に吸収させた後、酢酸塩緩衝液を加え、塩化物イオン電極を用いて測定する
ハロゲン化合物、シアン化合物、硫化物が共存すると影響を受ける
カドミウム・鉛の分析方法
適用濃度範囲:ICP質量分析<電気加熱原子吸光法<ICP発光分光分析法<フレーム原子吸光法
ICP 質量分析法以外は、定量下限値がカドミウム<鉛
ICP 質量分析法はカドミウム、鉛どちらも同じ濃度範囲)
①ICP質量分析法
誘導結合プラズマ中での鉛またはカドミウムおよび内標準物質(イットリウム)のそれぞれの質量/荷電数におけるイオンカウントを測定
- 硝酸の最終濃度が0.1~0.5mol/Lになるように調整
- カドミウムの妨害物質:酸化モリブデン・すず
- 鉛の妨害物質:酸化白金
- カドミウム、鉛、ニッケル、マンガン、バナジウムを同時に定量できる
②電気加熱電子吸光法
試料を前処理した後、マトリックスモディファイヤーとして硝酸パラジウム(Ⅱ)を加え、電子加熱炉に注入し、乾燥、灰化、原子化し、波長228.8/283.3nmの吸光度を測定してカドミウムまたは鉛を標準添加法によって定量
③ICP発光分光分析
試料溶液を誘導結合プラズマ中に噴霧し、カドミウムまたは鉛の発光を測定
(波長214.438/220.351nm)
- トーチおよび誘導コイルを用いてプラズマを発生させる
- プラズマを形成するためのガスはアルゴンを用いる
- 分析用試料溶液の調整には湿式分解を用いる
- 妨害物質:ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム(高濃度)
④フレーム原子吸光法
試料溶液をアセチレンー空気フレーム中に噴霧し、カドミウムによる原子吸光/鉛中空陰極ランプを光源として吸光度を測定(波長228.8/283.3nm)
- カドミウムの濃度が低いときは溶媒抽出濃縮を行い、酢酸ブチルに抽出
- 大量の亜鉛や銅が含まれている場合は、臭化水素酸で抽出
- 検量線を用いて濃度を測定、カドミウム標準液は硝酸に溶かす
- 妨害物質:アルカリ金属(カドミウムの場合、塩化ナトリウム)
有害物質の関連記事
【公害防止(大気)大気有害物質特論】有害物質の特徴(カドミウム・鉛・ふっ素・ふっ化水素・塩素・無機塩素化合物) – 【めざせ一発合格】工場資格まとめ
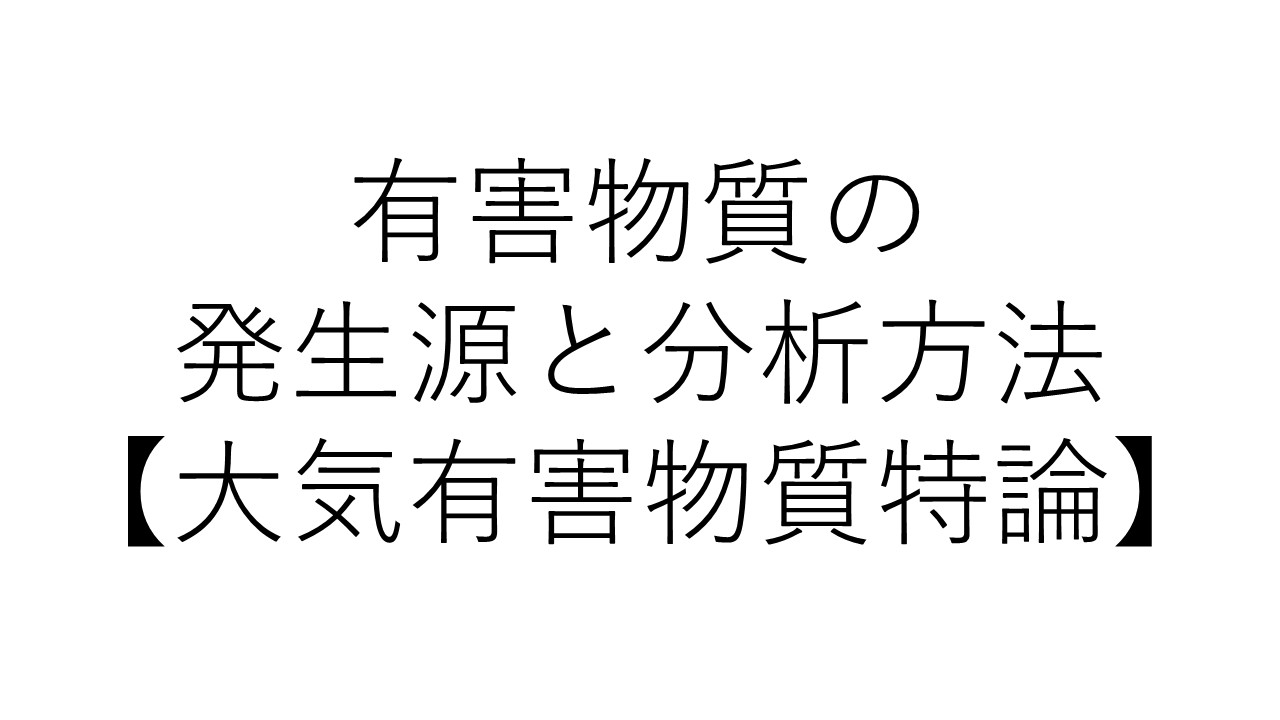
コメント