公害防止(大気)大気特論の「伝熱面の腐食とその防止対策」に関する覚えるポイントをまとめました
低温腐食
低温腐食とは
高温の燃焼ガスが冷却され、温度が酸露点まで下がると硫酸が凝縮し、液体硫酸により腐食が発生する。燃焼排ガス出口温度の低い発電用ボイラーや熱交換器のガス流れが一様でないと、局所的にガス温度が酸露点以下になって伝熱面を腐食する
高温腐食
高温腐食とは
重油中に含まれるバナジウム、ナトリウムなどの金属化合物が腐食成分として灰分中に残留。これが加熱器、再熱器などの高温伝熱面に付着、堆積して腐食を生じる現象
バナジウムアタックとは
バナジウムは高温になると溶け出して、燃焼装置の伝熱面に付着し、腐食させる。また、そこにナトリウムが存在すると燃焼ガス中のSOxと反応して硫酸ナトリウムとなり、これが腐食作用を促進する。
対策
- 高温部の伝熱面の表面温度を下げる
- 伝熱面の付着物を落とす
- ドロマイトなどの添加剤を注入して灰の融点を上げる
- バナジウム、ナトリウムの少ない重油を使用する
- 定期点検時などを利用し、スケールの除去を行う
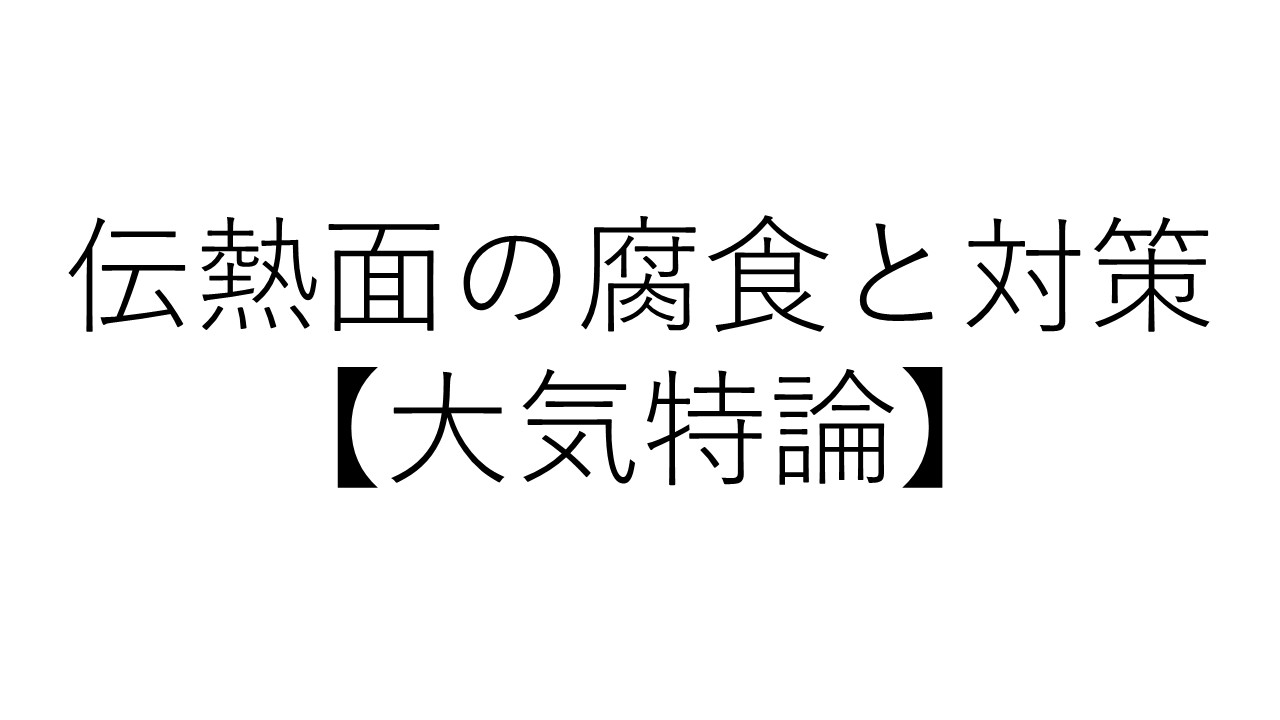
コメント