公害防止(大気)大気概論の「大気汚染防止法」に関する覚えるポイントをまとめました
大気汚染防止法についての穴埋め問題が出題されますが、すべてを覚えるのは困難です。
すべて暗記するのではなく、文脈から解答を選択できるようにしましょう
第 1 条 大気汚染防止法の目的
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
第 5 条2 総量規制基準
硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。
一. 特定工場棟に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料または燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料または燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分が低減するように算定される硫黄酸化物の量
二. 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められる重合した地表最大濃度が指定地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定される硫黄酸化物の量
第 13 条 ばい煙の排出の制限
一. ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者は、そのばい煙量、ばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない
二. 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあたっては、1年間)適用しない。
第 14 条 改善命令
都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる
第 16 条 大気汚染状況の常時監視
一. 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く)の状況を常時監視しなければならない。
二. 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視結果を、毎年度環境大臣に報告しなければならない。
三. 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
第 17 条 事故時の措置
ばい煙発生施設を設置している者または物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下、特定物質という)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下、特定施設という)を工場若しくは事業所に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損、その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に大量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない
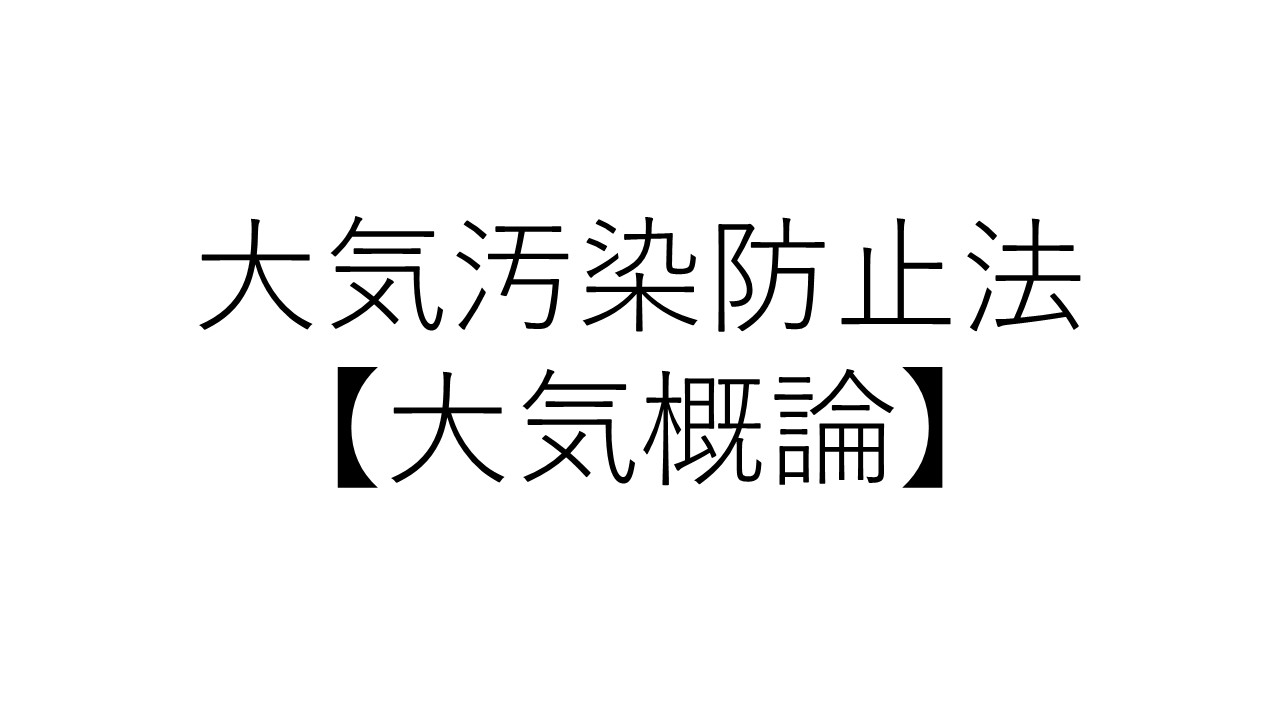
コメント